
趣向を凝らした審査方法と日本の料理界を代表する錚々たる顔ぶれの審査員団による厳正な審査で、新しい時代を切り拓く“食のクリエイター”を見出してきた「RED U-35」。12回目を迎えた「RED U-35 2025」のファイナルステージが、世界が注目する2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)のEXPOホール「シャインハット」にて開催された。世界に発信するにふさわしい記念すべき大会のテーマは「日本から世界へ〜EARTH FOODS 25」である。
11人目のグランプリRED EGG(2019年大会は該当者なし)の称号を獲得すべく、若き料理人が挑んだ一次審査の課題は、「日本から世界へ」をテーマに「EARTH FOODS 25」を使った料理と文章で自らのビジョンを表現すること。「EARTH FOODS 25」とは、食の未来をより良いものにするために、世界に広く共有したい日本発の食のリスト。米粉や豆乳、高野豆腐、山葵、山椒、干瓢など、日本の気候・風土によって育まれた独自の食文化を象徴する食材である。その価値と本質を再定義し、レシピとして広めることで、食文化のさらなる発展や、環境問題などさまざまな課題解決への貢献が目指された難題である。

大会プロデューサーの小山薫堂氏は、その意図を次のように説明している。
「過去に目を向けることで未来をより良くしようという狙いがある。我々にとっては当たり前の食材や食品、食の知恵に再びスポットライトを当てることで、世界中の人々はもちろん、我々日本人にも新しい価値を感じてもらいたい」。
日本に生まれ育った者、あるいは日本を舞台に活躍を続ける若き“食のクリエイター”は、このリストのどこに着目し、どのような価値を見出し、輝かしい食の未来に資する新たなビジョンを示してくれるのか--。「日本から世界へ〜EARTH FOODS 25」には、そんな期待が込められていた。
審査員を務めたのは、審査員長の狐野扶実子氏(食プロデューサー・コンサルタント)を筆頭に、脇屋友詞氏(Wakiya一笑美茶樓 オーナーシェフ)、佐々木浩氏(祇園さゝ木 主人)、君島佐和子氏(フードジャーナリスト)、辻󠄀芳樹氏(辻󠄀調理師専門学校校長、辻󠄀調グループ代表)、野村友里氏(eatrip 主宰/料理人)、小林寛司氏(villa aida オーナーシェフ)、吉武広樹氏(Restaurant Sola オーナーシェフ)。さらに、今大会には米田肇氏(HAJIME オーナーシェフ)が審査員団に加わった。
大阪ラウンドへ駒を進めた9/511
この難題に挑んだのは511名。多彩な経験をベースに、思考を重ねた末に導き出された回答の数々は、審査員団の頭を悩ませたことだろう。この最初の関門をクリアしたブロンズエッグ50名に新たに課せられたのは、一次審査で披露したメニューを120秒以内の映像で表現すること。一次審査同様、ハイレベルな戦いが繰り広げられた。二次審査である映像審査によって、挑戦者は早くも20名に絞られた。

シルバーエッグ20名が次に挑んだ三次審査のオンライン面談審査(グループディスカッションと、審査員との個人面談による2部構成)は、それぞれ10人が2グループに分かれてグループディスカッションからスタート。テーマは 「私たちが考えるEARTH FOODS 26」。つまり、「EARTH FOODS 25」に、どうしても加えたい一品を出し合い、最終的にメンバーの意見を調整してひとつに絞り、その理由を発表するというもの。
一次審査〜二次審査をとおして、日本に受け継がれる伝統食材への理解を深めた料理人らしい、本質をつく提案と議論に審査員が感心する場面も見られた。
また、他とは異なる角度から提案をする者、議論の円滑な進行に注意を払いながら自分の意見を提示するもの、あるいはすぐれたファシリテーターぶりを発揮する者など、料理人はそれぞれテーマの理解力、思考能力のみならず、それぞれの個性を存分に発揮。そんな充実した議論の末、グループAの提案は「蕎麦」、グループBの提案は「山菜」となった。

グループディスカッションを終えた挑戦者は続いて審査員との個別面談へ。与えられた時間は、「審査員たちにどうしても伝えたいこと」をアピールする1分と、審査員との質疑応答に充てる6分の計7分。緊迫した空気のなか、審査員たちはこれまでの過程で見落とされてきたかもしれない挑戦者の隠れた個性を見出すべく、さまざまな角度から質問を投げかけていた。
たとえば「グループディスカッションにおいてあなたが提案した食材とは異なる結論に至ったが、それに反論する意思はなかったのか?」など、その発言を問う場面も。限られた時間のなか、シルバーエッグ20名は懸命に自身の考えを披露するのみならず、審査員たちの質問に応答する際に、改めて自分らしさを見つめ直す貴重な機会になったはずだ。
審査を終えた審査員団は、大阪ラウンドへと駒を進める《シルバーエッグplus》を選ぶべく、すぐさま議論を始めるも、ほどなく結論に到達。評価のポイントとなったのは、料理の技量はもちろんのこと、議論を牽引し、あるいは調整し、自らのビジョンを言語化する能力の有無。己の思念を世界に向けて発信する力を有していると評価された9名が選出された。

【RED U-35 2025 シルバーエッグplus(三次審査通過者)】
(氏名/年齢/専門ジャンル/所属先名/所在地・活動地/肩書・役職)
・李 廷峻(35歳) 韓国料理 「HASUO」 東京都 オーナーシェフ
・イ テヒョン(32歳) 韓国料理、フランス料理 「HASUO」 東京都 スーシェフ
・向田 侑司(32歳) 中国料理 「ウェスティンホテル東京 龍天門」 東京都 料理人
・須藤 良隆(34歳) フランス料理 「La Plage」 新潟県 シェフ
・佐藤 歩(25歳) 日本料理 「菊乃井 鮨青 肉雲収」 京都府 料理人
・丸山 千里(31歳) フードクリエイター フリーランス 東京都 商品開発
・吉原 誠人(31歳) フランス料理 フリーランス(開業準備中) 山梨県
・田村 和儀(31歳) フランス料理 「wavie」 京都府 オーナーシェフ
・山名 新貴(29歳) イタリア料理 「KURKKU FIELDS (perus)」 千葉県 シェフ
※敬称略/調理順
※年齢はシルバーエッグplus発表日(2025年9月2日)時点
2日間にわたる激闘の始まり
2025年10月4日(土)早朝。《シルバーエッグplus》の9名が集合したのは、大阪・阿倍野の辻調理師専門学校。この日の試食審査によって勝ち残った5名だけが、翌5日(日)の大阪・関西万博で行われるファイナルステージに駒を進めることになる。
「私たちも本当に楽しみにしているので、みなさんも緊張することなく、楽しんで挑んでください」――緊張の面持ちで審査を待つ彼らは、審査員長の狐野扶実子氏の激励に奮い立ったかのように、各自準備を開始。一人目の挑戦者から厨房に移動し、試食審査がスタートした。

彼らのミッションは、「EARTH FOODS 25」の食材を使用し、一次審査で提案した料理をベースに仕上げたひと皿を審査員団に提供すること。制限時間は、調理時間と質疑応答を合わせて85分である。
いつもと異なる環境と、限られた時間のなかで、いかにして普段通りの実力を発揮することができるのか。料理の技術だけでなく、アクシデントをもチャンスに変える機転や適応力も審査の鍵を握る。
なお、試食審査室との仕切りは基本閉められ、審査員は調理室に入室して見学。進行後、審査員の希望もあり、短時間ではあるが仕切りを開いての見学を可とした(審査途中から数名)。手元の作業に集中しなければならない挑戦者は、普段とは異なる緊張感を感じていたはずだ。
トップバッターとして料理とともに審査室に姿を現したのは、三次審査のグループディスカッションにおいて流暢な日本語はもちろん、優れた思考力を発揮するなど、今大会における注目株の一人だった李 廷峻氏。東京・広尾で韓国の伝統料理をモダンに表現する「HASUO」のオーナーシェフである氏は、韓国の伝統料理「シッケ」を日本流にアレンジした「ミョルチ グクス(煮干しそうめん)」を披露した。スープは水出しの煮干し出汁をベースにさまざまなうまみを抽出したもの。さらに、熟成椎茸で作った自家製醤油で風味づけするなど、韓国流の足し算と、構成要素を絞り込むことで日本料理における引き算の美学を表現した。

「『日本から世界へ』というテーマをこの料理でどう発信したいか?」と、狐野扶実子氏からの質問には、「自分が日本に来て初めて感動したのは日本料理の“引き算”。それは、ただシンプルにするのではなく、食材の選定から調理、提供に至るまで一つひとつの工程にこだわりを込めることで成立するもの。日本での体験をと通じて最も感動したこの美学を、海外の料理人にも知ってほしい」と熱い想いをアピールした。

2番手は、トップバッターの李 廷峻氏がオーナーシェフを務める「HASUO」のスーシェフ イ テヒョン氏。「韓国と日本の素晴らしい発酵文化を料理で繋げて、世界へ届けたい」と語るイ氏は、韓国のカンジャンケジャンのタレに漬け込んだマグロの天身にわさびと山椒を忍ばせた軍艦巻きと、甘エビに日本の味噌で風味付けしたビスクリゾット、そしてキムチで爽やかな酸味を添えたキンパを組み合わせた「韓国的軍艦巻きとキンパ」を披露……。しかし、制限時間内に料理が完成することなく審査は終了。イ氏は、厨房を出ることなく戦いを終えた。

「表現したいことが多すぎて間に合わなかった。これは自分の責任。ただ、最善を尽くして頑張った」と、額に汗を滲ませながら反省の意を示すイ氏。審査終了後、救済措置として10分間の時間を与えられた氏は、狐野扶実子氏から「間に合わなかったのは残念だったが、完成した料理は酸味が効いていておいしかった」という言葉を受け、ようやく本来の笑顔を取り戻した。

3番手は、三次審査の個人面談で「変人であり続けたい」というアピールとともに存在感を示した「ウェスティンホテル東京 龍天門」の料理人 向田侑司氏。「炎との対話」を大切にしてきた氏が、「焼きおにぎりのようなものをイメージした」と語る、「好風」と題されたひと皿のテーマは「香り」だった。鴨肉には麹と中国酒で風味づけし、豚バラ肉は香ばしく焼き上げ、味噌の風味を引き立てた。「中国料理において、香りは重要な要素のひとつ。日本において中国料理を追究する料理人として、中国にはない日本ならではの香りや旬の食材を生かした中国料理を表現した」。麹香るひと皿には、中国料理人らしいテクニックと想いが凝縮れていた。

野村友里氏の「火入れが技術的なポイントだと思うが、この料理の一番の肝は何か?」という問いには、「今回は調味料が肝になっている。味噌そのものを食べていただくために、自分の焼き加減を活かした」と真摯な姿勢を伝えた。

「まずはクロモジの枝を折り、香りを堪能してほしい」とプレゼンをスタートさせたのは、4番手に登場した新潟・佐渡島出身の「La Plage」のシェフ 須藤良隆氏。金色の皿に盛り付けられた「佐渡の埋もれる宝」と題された料理は、山海の恵み、伝統文化、自らのルーツをフランス料理に昇華させたもの。ふぐを特製の塩麹でマリネし少し炙ることで、生と焼きの香ばしさのコントラストを強調。佐渡に伝わる河豚真子の粕漬け文化へのオマージュとして、発酵によるうまみを重ね、幼少期からの“食の記憶”をひと皿に見事に表現してみせた。

「フランス料理の素晴らしさとは?」という辻󠄀芳樹氏の質問に対し、「見た目や風味など、五感で楽しめるところがとても好きです」と答えるも、表情を崩さない󠄀辻󠄀氏の反応に戸惑ったのか、「…違いますか?」と不安げに語りかける須藤氏の姿に、緊迫した会場の空気が和む場面も。氏の人柄が垣間見えた瞬間だった。

日本料理の真髄ともいえる椀もので勝負に挑んだのは、5番手に登場した京都・東山の日本料理店「菊乃井 鮨青 肉雲収」所属の佐藤歩氏。氏が披露したのは、地元栃木の生産量日本一を誇る干瓢を素材に、精進出汁に豆乳クリーム、味噌シートなどでアクセントを加えたもの。「夏の物語 世界へ」と名付けられたこの料理は、幼いころに祖母と干瓢を採った夏休みの思い出から着想されたもの。そこには「日本の食文化や伝統的な食材を世界に広め、地方の未来に光を届けたい」という佐藤氏の強い想いが込められている。

「一次審査からメニューを変えても良かったはずだが、それでもこの料理で挑んだ理由は?」という佐々木浩氏からの問いに対し、「この料理で発信したかったことは、夏休みに朝起きて、おばあちゃんと一緒に干瓢農家の手伝いに行った、その風景を守りたい、届けたい思いが強かったから、今回は特別に変えずにこの審査に挑んだ」と、落ち着きのある口調で回答。しかし佐々木氏から「おいしかったが、お椀自体がぬるい。お椀料理は熱々で出すのが基本だ」と指摘され、佐藤氏は悔しげな表情を浮かべていた。

6番手に登場した丸山千里氏は、企業や生産者の依頼に応じて、料理人の知見を生かした商品開発に携わるフードクリエイターだ。そんな丸山氏が披露したのは、熊本県産の抹茶を用い、少量の生クリームと山椒、青唐辛子でアクセントを加えた「蟹と柑橘の抹茶ラーメン」。「慣習にとらわれることなく日本の食材の新たな魅力をアピールしたい」と語る丸山氏が着目したのは、抹茶の持つうまみ成分とコク。鶏ガラのうまみとの相乗効果で化学調味料に頼らない力強い味わいとなり、審査員をうならせるひと皿となった。三次審査の個人面談で「食材の価値を最大限に引き出し、驚きと発見のある食体験を大切にしている」と楽しげに語っていた丸山氏の渾身の自信作といえるだろう。

「“フリーランス”という肩書きについてどう思うのか?」という辻󠄀芳樹氏の問いに丸山氏は、「少し悩んだ時期もあった」と答えながらも、「リクエストに十分に応えることができず、不甲斐なさを感じたこともあった。しかし、食材の背景・価値を知ってからは、自分らしい料理を楽しく作れるようになった」と語った。

7番手に登場したのは、山梨県でレストランの開業準備をしている吉原誠人氏。4つのオリジナル麹で「無限」の可能性と自然の循環を表現した鱒(富士の介)料理で勝負に出た。「この料理は北海道で鮭が遡上する姿を見たのがきっかけ。それをクマが食べ、クマが生息する野山が育むキノコ、野草など豊かな自然の循環をイメージした」。天然のタモギタケで作ったキノコ味噌で鱒をマリネし、「クルマバソウの飯寿司」をベースにクリームバターでつなぎ、お酒を使わずに麹の発酵パワーを生かしてやさしいソースに仕上げた。そんなひと皿には、日本の食材の魅力、独自の発酵文化を世界にアピールしたいという吉原氏の想いを込められていた。

吉武広樹氏から「鱒と麹のソースを混ぜ合わせることをしなかったのはなぜか?」と問われると、「朧げな『無限』を表現したかったから。19歳の時に渡ったフランスでは、そこでさまざまな文化が交ざりあい、色んな食材が使われていることを知った。自分が思うフランス料理を日本の食材で作り上げたかった」と、確固たるアイデンティティを貫いた。

8番手は、2024年12月に京都・花園でフランス料理レストラン「wavie」をオープンさせたばかりのオーナーシェフ 田村和儀氏。氏が披露したのは、フランス料理をベースに、山菜の苦味を引き出し、グルテンフリーかつ動物性不使用に仕立てた「ひと巻きの風土〈秋分〉」と題された料理。「海外のゲストなど、どんな方に提供しても食べていただきやすいものとはなんだろう? まずはそこから構想をスタートさせた」という、ジャンルレスで味わい深い料理には、秋の味覚と静かな闘志が包み込まれていた。

佐々木浩氏からの「自分がこの料理を出そうと思った理由は何か?」という問いには、「食べやすさを重視して米麹を使いたかった。これまであまりチャレンジしてこなかったが、苦手だからこそ自分がやっていなかったことに挑戦したかった」と真剣な眼差しで答えを出した。

最後に登場したのは、千葉・木更津にあるKURKKU FIELDS内の循環型レストラン「perus」のシェフを務める山名新貴氏。地元鳥取県の先輩が製作した灰の釉薬製の器で披露したのは、自社農園や近隣地域で生産・水揚げされた食材を使用した漬け物料理。「日本料理の蕪蒸しから着想した」というこのひと皿の主役は、ホエーに漬けられた蕪である。「縁の下に咲く〜Autumn〜」というタイトルには、そんな意味が込められていた。また、ふぐと生ハムでとった出汁とカモミールによる香りを組み合わせることで、異なる文化の融合を表現。世界と日本をリンクさせ、食の無限の可能性をアピールした。

「野菜の漬物を使っているが、この料理の主役はふぐなのか?」という狐野扶実子氏の鋭い質問に、山名氏は「この料理の主役は個人的には蕪だと思う。ふぐは口の中に飛び込んでくると食感も良いが、蕪の方が味の主張が強い。だから蕪がメインだと伝えたい料理にした」と明確に答えた。

実力伯仲の戦いは、審査員を悩ませることに。「RED U-35は世界に何を発信するべきなのか? これらを明確にしないとRED U-35の本来のメッセージ性が失われていまう。その点を考慮しながら選ぶのが、私たち審査員の責任である」という審査員長・狐野扶実子氏の言葉に、この大会の意義を改めて確認する場面も見られた。
その結果、際立つ個を明確にアピールした下記の5名がGOLD EGGに決定し、翌日のファイナルステージへの切符を手にした。
・佐藤 歩(25歳) 日本料理 「菊乃井 鮨青 肉雲収」 京都府 料理人
・須藤 良隆(34歳) フランス料理 「La Plage」 新潟県 シェフ
・丸山 千里(32歳) フードクリエイター フリーランス 東京都 商品開発
・向田 侑司(32歳) 中国料理 「ウェスティンホテル東京 龍天門」 東京都 料理人
・李 廷峻(35歳) 韓国料理 「HASUO」 東京都 オーナーシェフ
※敬称略/ゴールドエッグNo.順
※年齢はゴールドエッグ発表日(2025年10月4日)時点

最後の関門は7分間のプレゼンテーション
翌10月5日(日)の早朝、大阪は小雨のぱらつく曇り空だった。しかし、10月13日(月)に閉幕を控えた大阪・関西万博会場は、訪れる人々の熱気に包まれていた。そんな中、大阪・関西万博のEXPOホールで「RED U-35 2025」ファイナルが開催された。RED EGG誕生の瞬間に立ち会うべくつめかけた1000人以上の観客が見守る中、ステージ上での公開プレゼンテーションによる運命の最終決戦が行われた。

最後の舞台に立つ選手たちのミッションは、「⾷べるって何?」をテーマに、自らの想い、アイデア、未来へのビジョンを表現すること。与えられた時間は7分間。どのようなメッセージを、どのような方法で伝え、いかにして観客を魅了するのか--そのスタイルは自由である。次世代の日本の料理界を牽引する料理人にとって、この舞台は未来を切り拓く発想力とビジョンを世界にアピールする発信力を試す絶好の場となったはずだ。

会場の注目が集まる中、トップバッターとして登場したのは、佐藤歩氏である。今回のファイナリスト中最年少ではあるが、年齢を感じさせない落ち着いた語り口で「あなたの好きな食べ物は?」と観客に問いかける授業風のプレゼンテーションを展開した。「僕がこのテーマで伝えたいのは、食べることによって作った人もみんな幸せになれるということ。 料理人だけでなく、生産者などさまざまな人たちと繋がりながら、この食べるという行為に幸せを感じることができると、僕は信じている」と、佐藤氏は食べることで広がる“幸せ”について語った。

2番手の須藤良隆氏は、ふぐの粕漬けなど地元の伝統料理を未来に残したいという想いやそのための島留学プロジェクトの構想を明かし、佐渡島の食文化と伝統の継承の必要性を訴えた。「佐渡のような地方は、やはり“伝統”が武器。 この島には世界でも類を見ない食文化があるが、その技術を受け継ぐ職人はごくわずか。その伝統を途絶えさせないために、私は将来料理で島留学をはじめたいと考えている」。須藤氏の熱い想いは審査員にも届いたはずだ。最後に、ステージ上に用意された佐渡島の伝統芸能である鬼太鼓を力強く叩き、島の魅力を音で表現して観客を魅了した。

唯一の女性ファイナリストである丸山千里氏は、三次審査で披露した「蟹と柑橘の抹茶ラーメン」を中心に、これまで開発してきた商品紹介を通して、そこに至るまでの体験や、生産者との出会いから生まれた食材への想いを、壇上のスクリーンに映し出された生産者や食材の写真を背景に語った。「日本の食材を未来に繋げていくことが、私が料理人としてこの先もずっと取り組んでいきたいこと。もし私がRED EGGに選ばれたなら、自信作の一つであるこのラーメンを商品化してみなさんに届けたい」。失われつつある日本の食材や食文化に新たな光をあてるための活動を続けていきたいというビジョンを明確に提示してみせた。
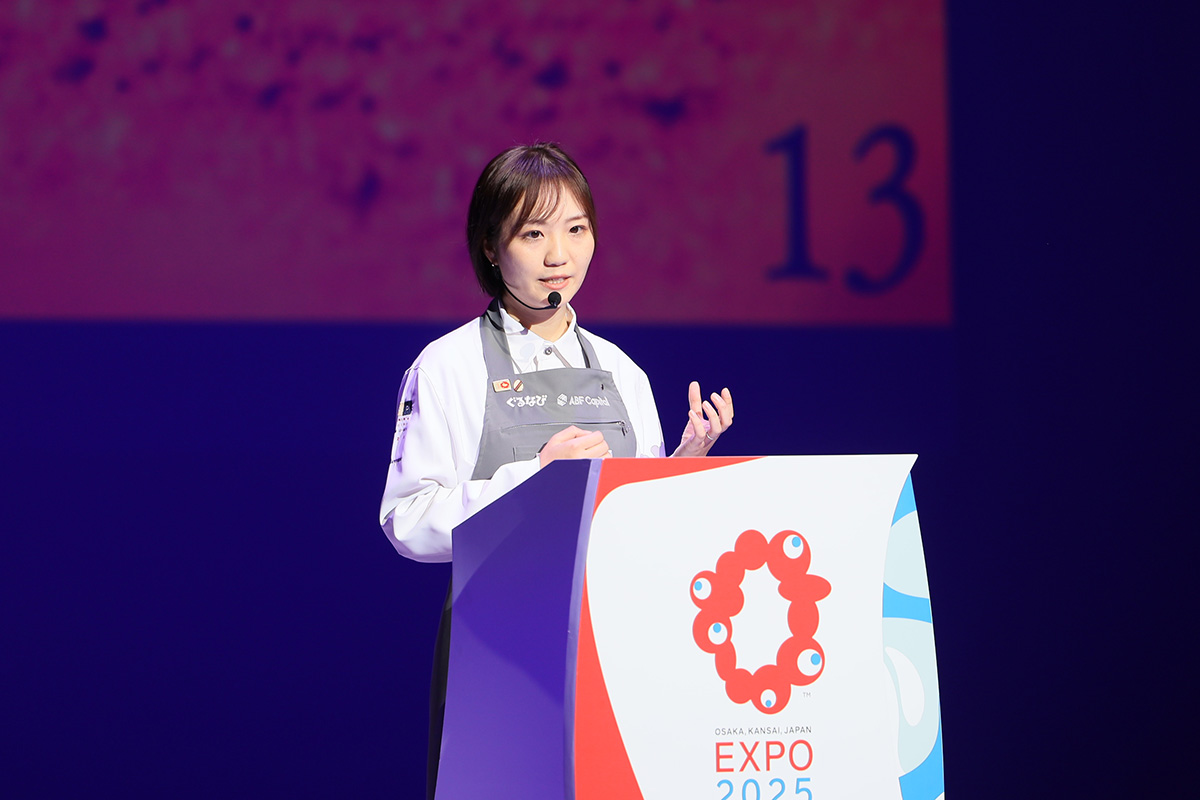
続いて登場した中国料理人の向田侑司氏が用意したのは、地元・岐阜県下呂市で栽培が盛んな品種の異なる3種類のトマト(農薬や化学肥料が使われたものと無農薬のもの)。試食を促された審査員の小林氏のコメントをもとに、それらの味の違いや特徴を説明。その意図について、向田氏はこう説明した。「どこで誰が、どんな想いで、どのように育てたものなのか――値段だけではなく、そういった目線で食材を選ぶことで、食の楽しみはさらに広がっていくはず。より良い明日のためにも、そんなことを考えてもらいたい」という向田氏の料理人らしい真摯な問いかけは、多くの人の心に響いたことだろう。

ラストの李廷峻氏が繰り広げたのは、AIとの会話劇だった。たとえば、「食べるということはどういうこと?」、「はい、食べるとは食べ物を口腔に取り込み咀嚼し…」「いやいや、そういうことではなく……」というように、AIが導く答えに対して、李氏が肯定あるいは否定しながら進めるダイアログは、やがて核心に……。その結論は、「食べるというのは、あらゆる文化の中で最も生活に近く、変化を敏感に反映し、未来へ更新し続ける先端の表現である」というもの。ユーモアを交えた知性あふれるプレゼンテーションに、客席からは惜しみない拍手が送られた。
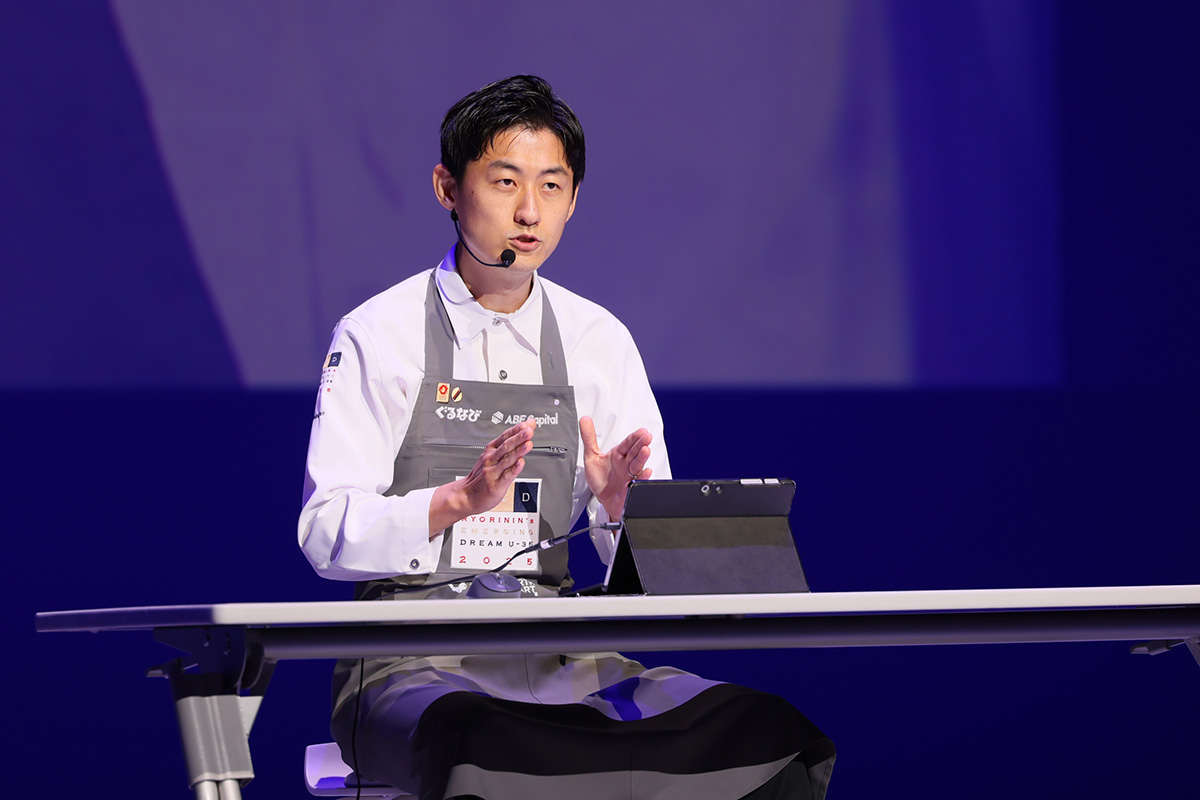
プレゼンテーションの後に行われた審査員との質疑応答では、総合プロデューサーの小山薫堂氏より、すべての挑戦者にある共通の質問が投げかけられた。たとえば、「料理人として20年後はどういう存在になっている?」や「料理人にとって一番大切にしていることは?」など、プレゼン内容とは無関係の想定外の質問に不意をつかれることも。しかし、さまざまな料理人と協力する大切さや、RED EGGになる覚悟など、ファイナリストはそれぞれ個性あふれる答えを毅然とした姿で披露。咄嗟の対応力と食す人への想い、さらにオリジナリティが試された瞬間だった。
ここで審査員たちは席を離れ、審査室にて最後の審議を行った。RED EGGにふさわしいのは誰なのか。 そして、食の未来を託せるのはこの日のプレゼン内容だけではなく、 半年間にわたって行われてきたさまざまな審査を通じて、総合的に判断された。議論では、「料理界とか社会にアタックする覚悟ができている」「人を繋ぐメッセージの作り方が上手」と賞賛する声がある一方、「RED EGGの責任を負えるか心配」と厳しい意見も飛び交った。果たしてRED EGGは誰の手に渡るのか。
存在感を増す料理人の多様なスタイル
同日午後3時。「RED U-35 2025」のフィナーレは、作曲家 千住明氏プロデュースのスペシャルライブによって、華々しく幕を開けた。ジャズピアニストのRINA氏とサックス奏者の中林俊也氏によるジャジーなアレンジで演奏されたのは、千住氏作曲の「RED U-35」テーマ曲“CHALLENGERS”。 希望に満ちた旋律が会場のボルテージをさらに高めていた。


そして、壇上に現れたのは戦いを終えたファイナリストの5名、そして最終審議を終えたばかりの審査員団である。「とても白熱した最終審査でした」という小山薫堂氏の一言に、緊張の面持ちで耳を傾ける挑戦者。ドラムロールが途切れ、静寂に包まれたステージ中央でスポットライトに照らされたのは、須藤良隆氏だった。
2日間に渡り濃密な時間を共にしてきたファイナリストたちが驚きの表情を隠せない須藤氏を囲み、互いに健闘を称え合った。審査員長の狐野扶実子氏からRED EGGのメダルを首にかけられた須藤氏の表情には、喜びと安堵の笑みが浮かんでいた。

「とても驚いています。ここまで来られたのは、支えてくれるスタッフ、家族、仲間のおかげ。これからも一生懸命精進して、食の未来を考え、佐渡の食文化を広める活動にさらに注力していきたい」。須藤氏の喜びの言葉は、会場に力強く響いていた。
審査員長の狐野扶実子氏は、「佐渡のみならず、日本、そして世界の食を盛り上げていただきたい。料理界に新しい風を吹かせてくれることを期待しています」と、エールを送った。

一方、準グランプリに輝いたのは、丸山千里氏。レストランに所属せずフリーランスのフードクリエイターとして活躍する丸山氏らしい視野の広さや課題抽出力を武器に、食材の新たな価値を発信し続ける真摯な姿勢と、食の可能性を広げたいという強い想いが高く評価された。
丸山氏は、「これからも日本の食材の素晴らしさを料理を通して伝えていきたい。知識や技術をさらに高めて美味しいものを生み出し、食の未来に貢献できるように精一杯頑張っていきたい」と語った。感極まる様子の氏に、会場からは惜しみない拍手が送られた。

「料理人の活躍の場がさらに広がっているのが最近の傾向。レストランだけでなく、機内食を製造する現場や教育の場など、さまざまなスタイルでフードクリエイションに携わる方が今後もさらに増えていくはずです」と、狐野扶実子氏は業界の新たなあり方とそこで活躍する若い料理人の活躍に期待を寄せた。
そんな従来の料理人としての領域を超え、食の発展への貢献を期待して贈られる「滝久雄賞」には、清野 桂太氏(30歳/イノベーティブ/東京都 フリーランス)が、女性料理人の活躍を支援し、様々なキャリアや働き方に光を当てるため、今後に期待できる女性に贈られる「岸朝子賞」には、丸山 千里氏(32歳/フードクリエーター/東京都 フリーランス)が輝いた。
さらに、優れた技術をもつ料理人やサービスマンの独立開業や事業展開を支援する株式会社ABF Capitalが、「いつか自分の理想の厨房(キッチン)をもちたい」、「自分の世界観を表現する店をもちたい」という夢や志を持つ料理人を応援するために設けられた「ドリームキッチン賞 by ABF Capital」には、福島 紗弥氏(28歳/専門 創作料理/スペイン「Txispa」料理人)が、日本航空株式会社(JAL)とのコラボレーションメニューを提供できる「Global Experience賞 by Japan Airlines」には、佐藤 歩氏(25歳/専門 日本料理/京都府「菊乃井 鮨青 肉雲収」料理人)が輝いた。


総合プロデューサーの小山薫堂氏は、「今大会、大阪・関西万博で開催できたことに感謝したい。本日ご来場いただいたみなさまにもこのコンペティションを通して、食の尊さを感じていただけたら幸いです」と大会を締めくくった。
大阪・関西万博会場にてフィナーレを迎えた記念すべき「RED U-35 2025」は、日本が誇る豊かな食文化と、その明日を担う料理人たちの輝かしい個性を世界にアピールしたはずである。次回大会では、どのようなドラマが待っているのか、次なる若き才能の登場に世界の注目が集まる。

text by Moji Company / Photos by Jiro Hirayama
RED U-35 2025受賞者一覧
《RED EGG(グランプリ)》須藤 良隆(新潟県「La Plage」シェフ)
《準グランプリ/GOLD EGG》丸山 千里(東京都 フードクリエイター フリーランス)
《GOLD EGG》李 廷峻(東京都「HASUO」オーナーシェフ)/ 佐藤 歩(京都府「菊乃井 鮨青 肉雲収」料理人)/ 向田 侑司(東京都「ウェスティンホテル東京 龍天門」料理人)
《岸朝子賞》丸山 千里(東京都 フードクリエイター フリーランス)
《滝久雄賞》清野 桂太(東京都 イノベーティブ フリーランス)
《ドリームキッチン賞 by ABF Capital》福島 紗弥(スペイン「Txispa」料理人)
《Global Experience賞 by Japan Airlines》佐藤 歩(京都府「菊乃井 鮨青 肉雲収」料理人)
RED U-35 2025
■ ORGANIZERS 主催:RED U-35実行委員会、株式会社ぐるなび
■ CO-ORGANIZER 共催:株式会社エービーエフキャピタル
■ CHEF SUPPORTERS:日本航空株式会社、ヤマサ醤油株式会社
■ SUPPLIER:辻調理師専門学校
■ CONSORTIUM:株式会社ぐるなび RED U-35 2025コンソーシアム
株式会社ぐるなび、株式会社エービーエフキャピタル、日本航空株式会社
※株式会社ぐるなび RED U-35 2025コンソーシアムは、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」のサプライヤーです